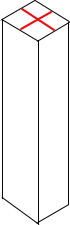境 界 の 管 理
測量して境界を確定するには多大な労力と高額な費用が掛かります。土地家屋調査士が依頼を受け、測量す場合は最初に登記所や市役所(区役所)等の資料と現地の調査をします。
現地の事前調査では境界杭を探し、1メートル以上の穴を掘ることもありますし、コンクリートの「たたき」の下に境界杭がある場合は何時間もかけて掘ることもあります。
その後測量をして資料と比較検討しますが、隣接関係者には境界確認を求め、道路境界については管理している官公庁に立会を求めなければなりません。やっと境界が確定したら今度は境界に杭(コンクリート杭、金属標 など)を入れ、境界確認書の取り交わしとなります。このように測量をし、境界を確定するには数多くの作業が必要になりますが、問題はその後の境界の管理です。境界標がいくら強固なものでも道路(水路)工事や周辺土地の工事により動いてしまうからです。特に地中を深く掘る工事に関しては注意が必要です。
また工事の邪魔になり、一時的に境界杭を抜いてしまった話を聞く事がありますが、一度境界杭を抜いてしまうと同じ位置に入れなおすことは簡単ではありません。。何れにしても問題が発生する前に土地家屋調査士に相談する事が大切です。
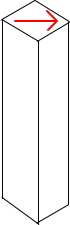
境界標は見えるように
境界杭がブロック塀の中に埋没していたり、また きれいに敷いたコンクリートやタイルの下だったりと、境界杭が見えないときが良くあります。これでは境界杭を入れた意味がありませんし、測量するときは境界を確認しなければなりませんので杭の周りを壊さなければなりません。
一度ブロック塀などを壊した場合元通りにはなりませんので、塀などの工事をするときは境界杭を見えるようにお願いします。
また土盛りをして境界杭が埋もれてしまう事がありますが、勝手に境界杭を持ち上げることなく土地家屋調査士に相談して下さい。
(参考)刑法262条の2
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識する事ができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。